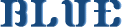 前編 前編
【蒼の祝福】――
言葉さえも知らなかったそれが何を差し、何を意味するのか……その瞳で見なければ決して知る事は出来なかったろう。
まるで幻のような、夢のような、あの儚く脆い出来事を――詩人のごとく言葉巧みに語って聞かせても、きっと誰にも信じて貰えないと思う。
この瞳で見た真実は、あの娘の鮮烈な最期と共に、この心を永遠に支配するのだろう――あの時、フォルスは直感していた。
◇ ◇ ◇
【赤のフォルス】といえば、その界隈では少しは名の知れた存在だった。賊上がりで滅法腕の立つその男は、燃え盛る炎のように赤い髪が目印。銃と剣を駆使し、謝礼さえはずめば何でも器用にこなす“便利屋”――それが通称【赤のフォルス】ことフォルス=ヴィーシニア、彼だった。
最初は“便利屋”なんてものを営んでいるつもりはなかった。それが、持ち合わせていた世渡り上手の性分を生かして小銭を稼いでいるうち、「いい仕事をする若僧がいる」という噂が人伝に広がり、いつの間にやら【赤のフォルス】なんていう通り名まで生まれてしまった。今では噂を聞きつけて、はるばる遠方から依頼に来る者さえあるほどだ。
そんな感じで順調に稼業として成立し、“便利屋”として世に存在すること早五年。フォルスの元に、奇妙な客が現れた。
客は若い娘で、アデイラ、アデイラ=リモーネと名乗った。小柄で細く、豊かな金の巻き髪を分けて高く結っているせいか、身体の細さに対して頭が幾分大きめに見える。不思議な形の長衣を身にまとい、布に包まれた本と思わしき大きな荷物を抱え、フォルスの元にやって来た。
その娘を奇妙だと感じた理由は、いくつかあった。
まず、瞳の色。五年の間に様々な地方へと足を運ぶほど忙しい身となったフォルスであるが、薄紅なんて色の瞳は生まれてこの方見た事がなかった。
そして、表情。年若く、秀でて整った顔立ちをしているのだが、徹底したかのように無表情なのだ。“美少女”では語弊があるように思う。そこまではつらつとした感じがない。むしろ、まるで人形――良く言えば神秘的、悪く言えば不気味、だろうか。
最後に、年齢。歳を尋ねたフォルスに対し、彼女はこう答えた。
「歳……そうですね、この“形”としては、十七年でしょうか」
奇妙な娘だった。そうとしか言い様がなかった。
困惑するフォルスを、薄紅色の瞳がじっと見つめ、そして言った。
「あなたは、何でもやってくださるそうですね」
そうだ、とフォルスが答えると。
「では、お願いがあります。わたしを、故郷へ還してください」
奇妙な娘の、奇妙な依頼に、フォルスは遠慮もなく頬を引きつらせた。
パチ、パチと。
暖炉の火が弾ける音が響く、さほど広くもない室内。
木製のテーブルを挟んで座る男女は、言葉もなくそこにいた。
テーブルと揃いの椅子に片膝を立てて座り、げんなりした表情の男は、赤い髪の先を指先でもてあそびながら、金色の瞳を対面する娘に向けた。
娘の薄紅色の瞳は、じっとこちらを見たまま、かれこれ数十分動いていない。そうすることで、相手が折れるのを待つかのように。
娘――アデイラは、腕利きの“便利屋”である【赤のフォルス】に願った。自分を故郷に帰してくれ、と。
奇妙ではあるが、もう子供ではない。故郷に帰るくらい、一人でできるだろうに――心中で呟きながら、フォルスは溜め息を零す。アデイラの耳にもしっかり聞こえているだろうが、彼女はあえてなのか知らないが、眉ひとつ動かさない。徹底した無表情だ。
過去に、訳ありのお偉い様から護衛の依頼をされたことはある。だが、アデイラの依頼はそれとは違うらしい。
何となく面倒な感じがして、フォルスは依頼を断った。
断ったのだが……故郷へ帰るつもりで来たから、引き返す場所など無いのだという。
その返答には、さすがのフォルスも頭痛がしてきた。ではなんだ。依頼を受けない限り、この娘は帰らないということか。ついでに、承諾するまでここに居座り続けるつもりか。
フォルスは、傍目に見てそこそこ良い容貌をしている。依頼に来た婦人やらに好意を抱かれたこともある。その果てに男女の関係を結んだ経験も、なくはない。相手が普通の女で、普通の依頼であったなら、この状況を多少喜べたかも知れないのだが。
「……それで? お嬢さんは、どこへ帰りたいっていうんだ」
仕方がない……盛大に溜め息を吐いてアデイラに向き直り、今度はテーブルに頬杖をつきながら、フォルスはとてもやる気のない表情で問いかけた。
駆け出しの頃は内容に関わらず何でもこなしたが、今は仕事を選べるようになった。だから、いかに興味を引かれたか、そしてその報酬次第で依頼を受けるようにしている。実際、あまり気乗りのしない依頼だし、あまり根つめて励んで疲れるのも面倒くさいと思ったのだ。
フォルスを見つめていた視線がゆっくりと動き、一度瞬くと、アデイラはその形の良い唇をかすかに動かす。
「……アズラク」
「は?」
聞き取れず、フォルスが再度問うと。
「アズラク。海底都市【アズラク】。わたしは、そこに還りたい」
はっきりと伝えられた名に、フォルスは思い切り顔をしかめた。
「聞いたこともない地名だな。それ、どこだよ」
だいたい、海底都市ってなんだ。そんなものがあるわけがないだろうが。フォルスは嫌味とも取れる言葉を続ける。年下の娘に対して少々大人気ないが、そうしたくもなる。面倒くさそうに、胡散くさそうに言い放つと、アデイラは傍らにあった包みを目の前に置き、汚れてくたびれた布をはぎ始めた。
中身は、予想通り本であった。
しかし、そこでまた奇妙な点を発見する。本はかなり古めかしい。表紙から中身から、全てが“遺物”とでも呼びたくなるほどの、年期の入った代物だった。
口を開けたまま、古びた本に釘付けになっていると。
「海底都市アズラクは、千年以上前から続く、選ばれし者のみが介入を許される場所。わたしはどうしても還らなければなりませんが、そこに至るまでに少々危険が伴います。ですから、あなたに護衛をお願いしたいのです」
願っている割に感情を宿していない薄紅の瞳が、じっとフォルスを見つめた。
「選ばれし者って……じゃあ、あんたは何者なんだよ?」
「今はまだ言えません。けれど、怪しい者ではありません」
それこそ千年以上も前から続いているなら、誰もが知っていそうな話だし、そのうえ自分で“選ばれし者”なんて言っているあたりが、どう解釈しても怪しいが……と、フォルスは心中で呟いた。
「あなたは、とても腕が立つと聞きましたが」
「まあ、そこそこ、人並み以上には」
「何でもやってくださるとも聞きましたが」
「それは内容と、報酬次第」
報酬、とアデイラが独り言のように反復した。
こちらにも生活があるのだから、それなりの要求はさせてもらう。危険の伴う護衛となれば尚更だ。
報酬面では全く期待できないだろうというのは、アデイラの様子から見て取れた。金銭的に余裕はなさそうだし、かと言って“女”を武器にしそうなタイプでもない。だから、こう言えば大人しく引き下がるかも知れないと、そう考えての事だったのだが。
「わかりました」
あっさりと納得し、アデイラは静かに頷いた。
「わたしを無事、アズラクへ還してくださったあかつきには……あなたに“祝福”を差し上げます」
そう言ったアデイラの表情のない薄紅の瞳が、一瞬だけ蒼く染まったように見えた。見間違いかと思って、何度か瞬きするうちに、彼女の瞳は元の薄紅に戻っていた。
「今、瞳が……」
呟くように言ったが、アデイラには聞こえなかったらしい。
フォルスは、やはり見間違いだと思うことにした。
「ところで、その“祝福”って何だよ?」
「……引き受けてくださるのならば、お答えしますが」
飄々とした顔がこちらを向いた。
そもそも、その祝福とやらが物なのか金なのか、知らずに引き受けるにはリスクが高すぎるではないか。こっちだって生きるために金銭が必要なのだから、下らない物をもらうなら断りたい。
「先ほども言ったように……」
ぽつりと呟きながら、アデイラは手元の本を開いて数ページめくり、目的の箇所を見つけると、読み進めるように紙面に指を這わせた。
「アズラクは、選ばれし者のみが踏み入ることのできる、神聖な場所。おいそれと真実を話すことはできません。しかし、あなたがわたしの依頼を受け、正式に護衛となってくださるのなら、“祝福”を受ける権利を差し上げます」
どう見ても、くたびれた紙面につづられた文章を読んでいるとしか思えないのだが。
――ものすごく、不安だ。
しかし、ここまで首を突っ込んだらやるしかないような気がしてきた。一応“便利屋”と名乗っているからには、どのような依頼であっても受けるべきだろう。それに、先程アデイラは“危険が伴う”と言っていた。よく考えてみれば、こんなどこからどう見てもか弱そうな娘を、そんな危険な場所に一人送り出すのも男としてどうかと思う。
しばし悩んだ結果――
「わかった。依頼を受けよう」
半ば渋々だが、フォルスは意を決した。
「その代わり、今話せることは全て話してもらう。俺だって、見知らぬ女のために命を落とすような真似はしたくないからな」
金色の瞳が少し苛立たしげに見遣ると。
「わかりました」
そう一言、アデイラはすっと立ち上がり、歩み寄ってきた。そうして目の前で立ち止まった少女を、金色の瞳が困惑気に見上げると――細く冷たい指先が頬に触れ、無表情の人形めいた奇麗な顔が声を上げる間もなく近づいた。
一瞬、混乱した。いや、誰でもこれは混乱するだろう。いきなり現れた見知らぬ娘に、いきなり口付けられたら、誰でも。
恋人同士のそれとは違い、軽く合わせただけの唇は、すぐに離れて行くかのように思えた。しかし予想に反して舌を差し込まれ、フォルスは思わず腰を浮かせた。たかがこの程度でたじろぐような子供ではないが……同時に、ひりっと焼けるような痛みが、喉を刺激したからだ。
「……っ、何する!」
触れていた唇が離れ、思い切り息を吸い込んだと同時に、フォルスは喉を押さえて咳き込んだ。喉の奥に感じた痛みが少しだけ残っていて、ひどく不快だ。金色の瞳が少女を睨み付けるが、自分からこんな事をしておきながらも、鉄壁の無表情は変化がない。
「変なモン飲ませたわけじゃないだろうな……!」
「いいえ、大切な護衛にそんなことはしません」
「じゃあなんだ。まさかこれが“祝福”だとか、ふざけた事を言うんじゃないだろうな」
「いいえ、これは“契約”です」
アデイラの態度は、まるで単なる“儀式”をこなしただけのような、そんな無感情なものだった。無遠慮で恥じらいもなく、むしろフォルスの方が内心で焦るほどだった。
「契約……?」
「これで、あなたはわたしを還すまで、わたしから離れられなくなった。その代わり、わたしはあなたの命令には従わねばなりません。それが“契約”」
なんだかもう、アデイラの言っている言葉全てが夢のような気がしてきた。
「わたしは、アズラクに還るまであなたを“主”として従います。そして最期に……“祝福”を差し上げます」
足元にひざまずき、アデイラは敬意を表すかのように深く項垂れた。
↑Top / Next →
Copyright(C)2008 Coo Minaduki All Rights Reserved.
|