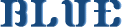 中編 中編
海底都市【アズラク】。
人とは異なる、人とは相成れぬ、人にはない力を宿す民が住まうという。
長い年月、人の世界で過ごし、やがて“時期”が近づくと故郷へ還る。
人の世で何を成し、何を求めるのか――地上に住まう人間が知ることはない。
アデイラは、物心ついた時には人の世界で過ごしていたらしい。だから、帰りたいとは言ってもアズラクの風景も何も知らないという。
それなのに、なぜ帰りたいと言うのか?
不思議に思ったフォルスが問うと、ただ“時期が来たから”と答えるだけであった。
なぜ十七年と言ったのか問えば、“物心ついた時から数えて十七年だったから”と答えた。
初めて帰る、己の故郷。それがどんな風景で、どんな危険が伴うのか……帰りたいと願う己さえ知らぬ、未知の世界。伝わる書物で全てを理解し、“時期”を悟り、“契約”を知り――ゆえに“祝福”さえも具体的に知らぬまま、アデイラは故郷を渇望する。果たして、一度として見たこともない場所を故郷と呼んでいいものか……代わりにフォルスが苦悩した。
アデイラの言葉通り。
“契約”を交わした後、フォルスはアデイラから離れられなくなり、アデイラはフォルスの命令に従うようになった。
アデイラが少しでも危険にさらされたり、一定の範囲から離れれば、焼けつくように喉が渇く。それが合図となった。
そして。アデイラはどんな些細な命令にさえも従順だ。我侭を言われるよりはマシだが、たとえば「もう少し右へ寄れ」とか「それを取ってくれ」といったような、日常的な言葉にさえも恭しく反応されると正直困る……そのように伝えたのだが、アデイラの反応はいま一つで、理解してもらえているのか謎だった。
【アズラク】を目指し、旅発ってから二十日が経過した頃。奇妙な“契約”で繋がれた二人は、海に程近い町・バハルにやって来た。海を目指さなければ、というアデイラの……要するに、書物の言葉に従ったのだ。
バハルは治安も悪く、お世辞でも“良い町”とは呼べない場所だ。犯罪行為は日常的だし、人攫いが現れることもある。特に見目の良い、若い娘は気を付けなければならない。
無法地帯ゆえに居住者・余所者の区別が付け難い点は有難いが、フォルスはともかく、アデイラは完全に街中で目立ってしまい、“余所者”と瞬時に区別されてしまったのが痛い。
アデイラは、【アズラク】の民。彼女が持つ書物によれば、アズラクの民は人とは異なる存在だという。どこからどう見ても普通の娘の形をしているのだが、やはり表情は無く、行動も不可解なので、何を考えているのか分かりづらい。
金の瞳がじっとアデイラの横顔を見下ろすが、気付いていないのか彼女は真っ直ぐ前を見つめたままだ。
人と異なる存在だからなのか、アデイラはとても綺麗な顔をしている。こうして街中を歩いていても、すぐに視線を集めるほどだ。
女の好みは特にないし、人の選り好みもしない方だが、まあせっかく護衛するならば美少女の方が気分もいい。これでもう少し愛嬌があれば文句なしで、さらに護衛のしがいがあるというものだが……と考えて、フォルスは眉間にしわを寄せた。別に、この娘が無表情であることに何の不都合もないではないか。
「頼むから、勝手にフラフラしないでくれよ」
「はい。わかりました」
アデイラは素直に応じたが、表情があまりにも“無”なため、フォルスは思わず溜め息を零した。
古びた宿に部屋を取り、一休みしている頃にはすっかり夜を迎えていた。一応若い娘相手ということで別部屋を考えたが、目を離すとどこかへ行ってしまいそうな、そんな危うさがあったために仕方なく同部屋だ。案の定、気にかけていたのはフォルスのみで、アデイラは少しも気にしていないようだったが。
こういう無法地帯は、何処で何があるかわかったものではない。だから絶対に一人で部屋の外をうろつくなと命じると、アデイラはまたしても無表情であったものの、確かに素直に応じていた。
それなのに……
「全くどこへ行きやがった!」
焼けつくように乾いた喉を抑え、不快気に表情を歪ませながらフォルスは裏道を疾走していた。ほんのわずか部屋を不在にした間に、アデイラはどこかへ消えていたのだ。
自分で出かけたのかも知れないが、誰かに連れ出された可能性も考えられる。あれだけ目立っていたのだ、良からぬ事を考える馬鹿が現われてもおかしくはない。
引き離された危機を感じ取るのは、ある程度の距離が必要である。たとえば同じ建物内では関知しないらしい。しかも、喉の渇きはその距離に応じて酷くなる。つまり、アデイラは宿からかなり離れた場所にいるということだ。
裏道にはガラの悪い男たちがひしめいていた。何度か絡まれたが、逆に銃をちらつかせて脅しつつ、ついでとばかり、目立つアデイラの風貌を頼りに問いただすと、浜辺の近くで見かけたという情報を手に入れた。その後お約束的に“情報料”を請求されたが、喉の渇きに伴う苛立ちに身を任せて全て殴り倒してやった。
浜辺にやって来るやいなや、ただでは済みそうにない状況を目の当たりにし、フォルスはすぐさま銃を抜いた。アデイラは、複数の男に囲まれていた。ざっと見て五人、他に仲間がいないとも限らないが。
「俺の連れに何の用だ」
銃を向けつつ声をかけると、男達と共にアデイラがこちらを振り返った。こんな危機的状況の中でも表情を変えない彼女は、感情が欠落しているのではないかと思う。それはどうでもいいが、言ったそばから迷惑をかけるのだけはやめて欲しい。何のための“契約”なのだか。
思い切り戦闘態勢のフォルスを見て、男達も銃を抜いた。
「何言ってんだ、おまえ。俺達はこのお嬢さんに海までの道を聞かれたから、親切に教えてやっただけなのによ」
男の一人が卑しげに笑いながら言った。どう見ても道案内だけで終わらせるつもりはなかったとわかるではないか。
「そうか、そいつはご苦労だったな。だったらもう用は済んだだろう。さっさと行け」
引き金に指をかけつつ、金の瞳が睨む。しかし、男達はニヤニヤと薄ら笑いを浮かべているだけで、一向に引き下がる様子がない。
わずかに警戒する。五人程度なら素早く撃ち抜ける自信はあるが、アデイラに危害が及ぶのは避けなければならない……そんな風に考えて、ちらとアデイラに視線を向けると、彼女にしては珍しく表情を変えた。薄紅の瞳がわずかに見開かれたその意味を悟る前に――銃声が響き、胸に大きな衝撃を受けた。
血飛沫を飛ばし、フォルスの身体が前にのめる。心臓を撃ち抜かれたのだと気付く前に頭は真っ白になっていた。
「はははは! ひとりでのこのこやって来るなんて、馬鹿じゃねえの?」
背後から撃ち抜いたらしい男達の仲間が、下卑た笑いを上げた。けれど耳鳴りがひどくて、笑い声なんか聞こえない。
寒い。流れ出る血は確かに熱いのに、徐々に体温は下がり、身体が冷え切ってゆく。指先さえも動かせないほど、あっという間に全てが止まってゆく。これが死ぬということなのだ――そう悟ったフォルスは、しかし違和を感じてびくりと身体を震わせた。
霞む視界に映し出した、己の手。血に塗れたはずのその掌が蒼く見えたのは、死が近いゆえの幻覚か。
「これだから他所者は困るよなあ」
「まあ、邪魔者もいなくなったことだし、お楽しみと行きますか」
男達がアデイラを囲み、その華奢な肩に手を触れようとした時。
再び銃声が響き、何事かと振り返った男達の一人が背後に倒れた。肩を撃ち抜かれたその男は、激痛に身悶え、浜辺でのたうち回っている。
男達の顔が驚愕に引きつった。
それもそうだろう。さっき心臓を撃ち抜かれて死んだと思った男が、立ち上がっているのだから。
流出した“赤”は、“蒼”へと色を変えて体内へと逆流してゆく。まるで身体の芯から冷やされているような感覚に震えが起こった。それでもフォルスは銃を構え、今一度男達を睨み付けた。その様はさぞ異様に映ったことだろう。
「ひ、ひいいっ!」
「ば、化け物か!」
男達は蒼白になり、恐れを成して慌てて後退する。
その脇をすり抜けて、無表情のアデイラが歩み寄って来る。
「死にたくなければさっさと行け!」
手の届く範囲までアデイラが戻ったのを見計らって一喝すると、男達は洩れなく奇声を上げながら逃げ惑って行った。
浜辺には静寂が戻り、打ち寄せる波の音だけが続く。
己の掌を今一度見下ろし、フォスルは眉をひそめた。血で染まっていた手は、何事もなかったかのように綺麗になっている。衣服こそ破れているものの、心臓を撃ち抜かれた穴はしっかり閉じていた。
「……これが“契約”か」
金色の瞳が、少女を睨むように見る。
アデイラは静かに頷いた。
「そう。あなたは、わたしをアズラクに還すまで死ねない。どんな傷を負ってもすぐに回復する。“儀式”はそのためのもの」
アズラクの民には不思議な力が宿っている。それは物理的な意味だけとは限らない。彼等の体液にも力はあり、ゆえにそれらを間接的に体内に入れる事により、力を分け与えることが可能だ。あの時のアデイラの口付けには、そういう意図があったらしい。
不思議、というよりは恐ろしい感覚だった。
「どうでもいいが、そういう事は早めに言ってくれ。本気で死んだと思ったぞ」
「わたしも、ついさっき知ったの」
「ああ、そうかい」
抱えていた本を軽く掲げたアデイラに、フォルスはがっくりと肩を落とした。
できればもっと学習しておいて欲しいものだ。
「ところで、何で勝手に出歩いたんだよ? 大人しくしていろと言っただろ」
しばしの間、アデイラはフォルスの視線に応えていたが、やがて視線を逸らして海を見つめた。
「……呼んでいたから」
「は?」
「海が、呼んでいたから」
薄紅の瞳が夜の海をじっと見つめていた。吹いて来た潮風が、豊かな金の髪を重たげに揺らす。風が運んでくる“呼び声”に聞き入っているのか、アデイラは微動だにしない。
「アズラクへの道は、あらゆる海から繋がっている。アズラクへの道が開けるのは、民が帰還するその時だけ」
まるで書物の文字を読み上げているような、淡々とした口調でアデイラが語る。
「あそこ」
細い指が示した先には、水面に映る月の影。
白く美しい満月が、波間でゆらゆらと揺れていた。
「水と月は我々の味方、力の源。今宵、道が開ける」
まるでの魔法の言葉のように一言呟いて。アデイラが一歩、また一歩と海の中へ踏み入ると、驚くべき事に、海が真っ二つに割れてゆく。
「嘘……だろ?」
驚愕の表情でフォルスは海を凝視していた。そうしている間にも海の裂け目は大きく、深くなってゆく。意志を持って自らアデイラを遠ざけるように退いてゆく様は、まさに壮観だった。
「行きましょう」
大海原の壁の中、アデイラが振り返る。
その瞳は、確かに蒼く染まっていた。
← Back / ↑Top / Next →
Copyright(C)2008 Coo Minaduki All Rights Reserved.
|